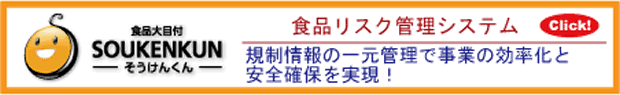
★「ポジティブリストで残留農薬を調べてみよう」でよくある質問
Q1. そもそも残留農薬ポジティブリストとはなんですか?
Q2. いつからポジティブリストが施行されたのですか?
Q3. 規制の対象はなんですか?
Q4. 農薬とはどういったものですか?
Q5. 誰が対象になるのですか?
Q6. 農薬を使用できなくなるのですか?
Q7. 残留農薬が少しでも含まれていたら違反になるのですか?
Q8. 暫定基準とは何ですか?
Q9. 暫定基準は“暫定”だから越えても違反にならないのですか?
Q10. 基準値に「1ppm」と「1.0ppm」があるのはどうしてですか?
Q11. 「含有不可」とあるのはどういう意味ですか?更新!
Q12. 基準値が示された農薬はどのくらいあるのですか?
Q13. その800種類の農薬は分析できるのですか?
Q14. 分析をしないと違反になるのですか?
Q15. 加工食品の残留農薬の分析方法はありますか?
Q16. それでは加工食品の基準はどうやって守るのですか?
Q17. 加工食品で基準値を越えてしまいました。違法ですか?
Q18. 基準値を越えてしまいました。ただちに回収しないといけませんか?
Q19. 海外から新しい農薬を使った作物を輸入することになったので(新しい農薬を開発したので)基準値を作ってください。
Q20. 加工食品の製造者です。どういった点に注意したらよいですか?
Q21. 食品の輸入者です。どういった点に注意したらよいですか?
Q22. 「残留農薬を調べてみよう」にある“検疫所マーク”がついた農薬だけ気を付けていればいいんですか?
Q23. 検疫所において命令検査になっている農薬が掲載されていません。
Q24. 今月の検疫所マークはどうなったのですか?
Q25. 食品工場の衛生管理で殺虫剤を使ってます。食品に混じったら違反になりますか?
Q26. 画面を印刷すると変な文字が出ます。
Q27. 「残留農薬を調べてみよう」の内容が他の機関のホームページや厚労省発表の内容と違っています。更新!
Q28. 基準値改正の更新頻度・ラグタイムは?
Q29. この「よくある質問」の回答根拠はどこにあるのですか?
Q2. いつからポジティブリストが施行されたのですか?
Q3. 規制の対象はなんですか?
Q4. 農薬とはどういったものですか?
Q5. 誰が対象になるのですか?
Q6. 農薬を使用できなくなるのですか?
Q7. 残留農薬が少しでも含まれていたら違反になるのですか?
Q8. 暫定基準とは何ですか?
Q9. 暫定基準は“暫定”だから越えても違反にならないのですか?
Q10. 基準値に「1ppm」と「1.0ppm」があるのはどうしてですか?
Q11. 「含有不可」とあるのはどういう意味ですか?更新!
Q12. 基準値が示された農薬はどのくらいあるのですか?
Q13. その800種類の農薬は分析できるのですか?
Q14. 分析をしないと違反になるのですか?
Q15. 加工食品の残留農薬の分析方法はありますか?
Q16. それでは加工食品の基準はどうやって守るのですか?
Q17. 加工食品で基準値を越えてしまいました。違法ですか?
Q18. 基準値を越えてしまいました。ただちに回収しないといけませんか?
Q19. 海外から新しい農薬を使った作物を輸入することになったので(新しい農薬を開発したので)基準値を作ってください。
Q20. 加工食品の製造者です。どういった点に注意したらよいですか?
Q21. 食品の輸入者です。どういった点に注意したらよいですか?
Q22. 「残留農薬を調べてみよう」にある“検疫所マーク”がついた農薬だけ気を付けていればいいんですか?
Q23. 検疫所において命令検査になっている農薬が掲載されていません。
Q24. 今月の検疫所マークはどうなったのですか?
Q25. 食品工場の衛生管理で殺虫剤を使ってます。食品に混じったら違反になりますか?
Q26. 画面を印刷すると変な文字が出ます。
Q27. 「残留農薬を調べてみよう」の内容が他の機関のホームページや厚労省発表の内容と違っています。更新!
Q28. 基準値改正の更新頻度・ラグタイムは?
Q29. この「よくある質問」の回答根拠はどこにあるのですか?
Q1. そもそも残留農薬ポジティブリストとはなんですか? (top)
A1. 平成18年5月以前、残留農薬はネガティブリストで規制されていました。ネガティブリストとは原則全て自由、残留してはいけない農薬だけをリストにしたものです。例えば海外で新規な農薬が使用されそれが残留した食品を輸入しようとしても差し止めることはできません。
そこで、原則全て禁止、使えるものだけをリストにしたポジティブリストの考え方に変わってきたのです。基本的にはいまの食品添加物規制の考え方と一緒です。
Q2. いつからポジティブリストが施行されたのですか? (top)
A2. 平成17年11月29日に告示され、6カ月の猶予期間をおいた後、平成18年5月29日から施行されました。
Q3. 規制の対象はなんですか? (top)
A3. 生鮮品、畜水産品、加工食品を含む全ての食品です。医薬品、食品添加物、ペットフード、口にしない工業製品などは対象外です。ただし一般に食品としても使用される食品添加物は規制の対象になります。
Q4. 農薬とはどういったものですか? (top)
A4. 農業で使う化学物質のことを指します。農作物に使う薬品(いわゆる農薬)、動物薬、飼料添加物が対象です。しかし下記のものは対象外にされています。
(1)国際的に安全性が認められたもの(ADIの設定が不要とされたもの)
(2)特定農薬 食酢、重曹、生物農薬など
(3)自然界に存在するものと同じもの アミノ酸、ミネラルなど
2005年11月29日現在65物質あります。 →除外物質リストへ
Q5. 誰が対象になるのですか? (top)
A5. 販売の目的で、食品を製造、輸入、加工、使用、調理、保存、販売する人です。
Q6. 農薬を使用できなくなるのですか? (top)
A6. 農薬を使うこととは全く別問題です。食品に残留する農薬が規制されるだけです。
Q7. 残留農薬が少しでも含まれていたら違反になるのですか? (top)
A7. 「食品から検出されてはならない」農薬があります。また基準に「不検出」と定められているものもあります。これらは、告示された方法で分析を行い検出限界値以上出たら違反となります。不検出リストはこちらをご覧ください。 →不検出リストへ
その他のものに関しては、食品ごとに残留してもよい農薬の種類と量が決められています。これがポジティブリストの基準値です。この基準値が示されたものは、その値以内であれば残留しても違反にはなりません。
基準値が示されていない食品や農薬に関しては、一律に0.01ppmを越えて含有してはならないことになっています。これが「一律基準0.01ppm」です。
Q8. 暫定基準とは何ですか? (top)
A8. 今回示している基準値のほとんどが暫定基準です。本当なら基準値は人が一生食べ続けても安全な量を科学実験で求め、それを食品安全委員会にかけるのが筋です。けれども食品安全委員会で検討できるものは年間10個くらいと言われています。これだと800種類の農薬を全て検討するのに、何十年もかかることになります。
そこで、既に海外に基準があるものや、世界で認められたもの(codex基準)などは、とりあえず暫定的にその値を使おうということになりました。これが暫定基準です。
Q9. 暫定基準は“暫定”だから越えても違反にならないのですか? (top)
A9. 暫定とはいっても、法律で定められた基準なので、越えれば違反になります。
Q10. 基準値に「1ppm」と「1.0ppm」があるのはどうしてですか? (top)
A10. 有効数字の問題です。
「1ppm」は小数第1位を四捨五入するので、0.5ppm以上1.5ppm未満の範囲となります。
「1.0ppm」は小数第2位を四捨五入するので、0.95ppm以上1.05ppm未満の範囲となります。
Q11. 「含有不可」とあるのはどういう意味ですか? (top)
A11. ポジティブリストに収載されていない農薬や食品は、一律基準0.01ppmが適用されますが、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない(昭和34年厚生省告示370号)とありますので、これらの物質は一律基準ではなく、含有不可と記載しています。
Q12. 基準値が示された農薬はどのくらいあるのですか? (top)
A12. 800くらいあります(複数の農薬が一項目になっているものもあり数え方によって変わります)。
Q13. その800種類の農薬は分析できるのですか? (top)
A13. そもそも全ての農薬の分析方法が確立していないし、標準品も揃ってないので、全部は無理です。
2006年5月末現在623種類くらいと言われています。
Q14. 分析をしないと違反になるのですか? (top)
A14. 食品に残留する農薬などの基準値が定められたのであって、けっして分析が義務化されたわけではありません。分析書がなければ取引を停止する、など言われるのはまさに不当な圧力です。
といっても応じないといけない状況があるのは承知してます。不当な圧力を排除する指導を国はやらないと言ってますので、自分たちで対峙していくしかありません。
Q15. 加工食品の残留農薬の分析方法はありますか? (top)
A15. 加工食品も分析しようと思えばできます。けれども加工食品の分析は、残留農薬以外にもさまざまな物質が含まれておりそれらが邪魔をするので(夾雑物質といいます)かなり困難です。お金と時間がかかり過ぎるという問題もあります。
Q16. それでは加工食品の基準はどうやって守るのですか? (top)
A16. 原料で判断します。原料が基準以内であれば最終製品も守られていると判断します(※※補遺)。しかし原料が既に加工食品である場合、どこまでさかのぼればいいかなど問題は残ります。原則は原点回帰だから農場まで戻ることになりますが、それは多分無理な話です。
※補遺
(平成18年5月29日食安監発第0529001号から抜粋)
(製造加工された食品において)一律基準を超えて残留する可能性がないものについては、食品衛生上の危害が認められない場合として、法第54条に基づく対応、行政指導の措置を取る必要がないと認められる場合もあるので、留意すること。
逆に言えば、最終的に一律基準を超えていない加工食品であっても、原料や原料として使用した加工食品が基準を超えていたら違反に問われ回収などの措置がとられる場合もあるということです。気を付けるに越したことはありません。
※※補遺
(平成19年2月27日食安発第0227001号から抜粋)
平成17年11月29日付け食安発第1129001号の追加改正
(9)改正後の一般規則の11について
食品規格が定められていない食品を原材料として製造され、又は加工される食品については、当該加工食品の原材料が一律基準に適合していれば、当該加工食品についても当該食品に残留する農薬等の残留値によらずに食品規格に適合するものと解し、一律基準の規制対象とならないものとして扱うこと。
要するに、原材料の基準が守られているならば、それを使った加工食品もOKということが明記されました。
Q17. 加工食品で基準値を越えてしまいました。違法ですか? (top)
A17. 乾燥などの濃縮工程が入っていて原料は基準を満たしているのに最終製品は越えてしまった場合は、違法にはなりません。都道府県の調査で工程などが加味され判断されることでしょう。最終製品が越えないに越したことはないのですが、製造方法をきちんと示し説明できるよう準備しておくことです。ただし故意に犯す、改善命令を無視するなど悪質な場合は違法と判断される可能性があります。
Q18. 基準値を越えてしまいました。ただちに回収しないといけませんか? (top)
A18. 基準値を超えても、公衆衛生上問題がないと判断されれば、回収命令は出ないでしょう。
しかし、企業が信用維持などで自主回収するのとは別の問題です。基準値を超えたことが明らかになったら、企業としては、回収する必要がなくても回収せざるを得ないのが現状です。
Q19. 海外から新しい農薬を使った作物を輸入することになったので(新しい農薬を開発したので)基準値を作ってください。 (top)
A19. 自分で毒性や安全性のデータなどを全て用意して、厚労省に申請してください。待っていても誰もやってくれないし自動的に登録されることもありません。また最低でも一年以上かかるのでお急ぎの場合はお早めに。
Q20. 加工食品の製造者です。どういった点に注意したらよいですか? (top)
A20. 全ての農薬を検査することは不可能ですから、まずは不検出項目が検出されないように気をつけてください。
あとは原料管理をしっかりすることです。原料メーカーからしっかり担保をとる、万が一の経済損失を逃れるため保険に入っておくなどでしょう。そうすればこれまで以上に新たな検査をする必要はありません。
Q21. 食品の輸入者です。どういった点に注意したらよいですか? (top)
A21. 海外の農薬使用状況はいつもチェックしていおいた方がいいでしょう。過去の違反事例を調べて蓋然性が高い農薬、農産物、食品も要注意です。他者が摘発されたときも要注意です。
Q22. 「残留農薬を調べてみよう」にある“検疫所マーク”がついた農薬だけ気を付けていればいいんですか? (top)
A22. 「残留農薬を調べてみよう」では検疫所の平成20年度モニタリング計画にある抗生物質、農薬に印をつけています。これはあくまでも年間計画です。他の物質でも違反が見つかればその都度検査命令が出ますし、メチレンブルー、クリスタルバイオレット、ブリリアントグリーンなどポジティブリストに収載されていない物質、抗生物質全般もモニタリング項目になっています。
また「初めて輸入されるような新規食品は積極的に検査すること」ともあるので、モニタリング計画だけ気を付けていればよいというワケではありません。
ただ、モニタリング物質は500以上あり、検疫所マークが要注意であることは間違いありません。
Q23. 検疫所において命令検査になっている農薬が掲載されていません。 (top)
A23. 例えば、中国から輸入されるネギはテブフェノジドの検査命令が出ています(2008年4月現在)。ところが「残留農薬を調べてみよう」のネギの項目にテブフェノジドは掲載されていません。それは、テブフェノジドがネギについては一律基準の農薬で、ポジティブリストに収載されていないからです。
「ポジティブリストで残留農薬を調べてみよう」はあくまでもポジティブリストから出発した情報であるため、検疫所モニタリング項目の全てが掲載されているわけではありません。どうぞご注意ください。
※補遺
平成18年12月19日から、検疫所から出ている輸入食品検査命令の情報も収載しました。
Q24. 今月の検疫所マークはどうなったのですか? (top)
A24. 平成18年度は、平成18年4月17日食安検発第0417002号別表第3により、月ごとの検査項目が公開されておりましたが、平成19年度以降に関しては一般に出回っていないようです。したがって、年間を通じた検査項目の一覧を掲載しています。
Q25. 食品工場の衛生管理で殺虫剤を使ってます。食品に混じったら違反になりますか? (top)
A25. 本来は“食品に残留する農薬”が規制対象なのですが、どこで混じったか区別することが難しいため、このケースでもポジティブリストの基準値が適用されることになります。
今後はこれまで以上に、食品にかからないような散布方法に変えるとか、濃度の工夫などが必要になってくるでしょう。
Q26. 画面を印刷すると変な文字が出ます。 (top)
A26. 2006年9月より全文検索を開始したため、隠し検索語を各ページの頭に入れています。印刷すると現れてしまいます。お見苦しいでしょうがご了承のほどよろしく御願いいたします。
Q27. 「残留農薬を調べてみよう」の内容が他の機関のホームページや厚労省発表の内容と違っています。 (top)
A27. 他機関のデータベースと比べ「不検出」の農薬が余分に入っているというご指摘を受けました。ポジティブリストには不検出農薬は入っていないものの、その食品から検出されてはならないのは明らかなので、敢えて加えています。
また、過去に暫定基準値が設けられていたものが改正で「一律基準」若しくは「含有不可」になった場合も敢えて表示してます。
さらには、全て手作業のため、入力ミスはあるかと思います。万全を期しておりますが、もしお気づきの点があれば誠に恐縮ですがメールでご一報ください。
Q28. 基準値改正の更新頻度・ラグタイムは? (top)
A28. 原則として、基準値改正の厚生労働省告示が官報に掲載される度に更新します。
当日朝、官報が発表された後に作業・確認して更新しますので、反映されるのは12時前後になります。改正量が多い場合、休日を挟んだ場合などはこれよりも遅れますので、ご了承ください。
Q29. この「よくある質問」の回答根拠はどこにあるのですか? (top)
A29. 現在掲載しているQAは、これまで厚労省の発表した資料、厚労省の説明会で出たもの、取材したもの、などをまとめたものです。
厚労省の発表した資料は、下記のページからご覧ください。 →厚労省HP食品中の残留農薬等へ
著作・制作 フジテレビ商品研究所